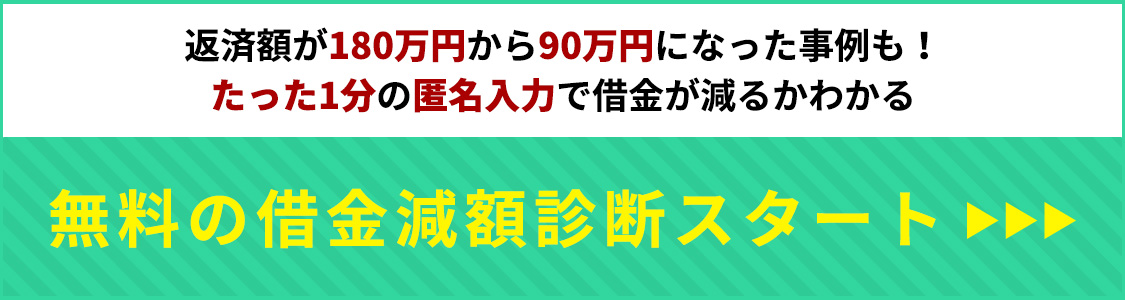グレーゾーン金利とは?みなし弁済とは?

グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは
日本における金利規定は、利息制限法と出資法の二つの法からなっています。出資法を超える利息を請求した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人は3000万円)以下の罰金が科されると定められており、刑事罰の対象となります。しかし、2010年の改正法が施行されるまでは、利息制限法を超える利息部分に関する請求は認められないとしても、罰則が定められていないため刑事罰の対象とはされていませんでした。グレーゾーン金利とは、このような利息制限法の上限金利以上であって出資法の上限金利以下の金利を示します。
改正前利息制限法金利上限
・元金10万円未満 年利20%
・元金10万円以上 年利18%
・元金100万円以上 年利15%
改正前出資法金利上限
・29.2%
改正後出資法金利上限(2022年改正)
・20%
みなし弁済とは
もっとも、グレーゾーン金利は、刑法上の罰則は科されませんが、民事上は違法な金利として支払いの義務は認められません。しかし、みなし弁済という制度によって、このグレーゾーンの悪用が助長されてきました。みなし弁済とは、債務者が任意で高い金利を支払ったとして認められれば、利息制限法の上限以上の金利であっても有効とするものでした。民事不介入の原則によって、刑法上の違法行為でなければ警察は借金問題に介入できません。よって、このような法律の抜け穴をうまく利用した貸金業者が、利息制限法に違反する高金利で貸し付けを行ったとしても有効とされてきたのです。
みなし弁済の要件
・貸金業登録を受けた貸金業者であること
・貸付時に契約(17条書面)を交付していること
・弁済時に受領詔書(18条書面)の交付をしていること
・借主が任意に利息を支払ったこと
・借主が利息であることを認識して利息の支払いをしていること
みなし弁済の否定
しかし、「最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決」によって、判例では、みなし弁済は完全に否定されることとなりました。それを機に、立て続けにみなし弁済を実質的無効とする判決が相次ぎ、法整備が行われ、立法においても2010年の貸金業法改正によって、みなし弁済の規定は撤廃されることとなりました。現在では、出資法上限金利は20%まで引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました。よって、2010年6月17日以降においては、貸金業者がこれを超える金利での貸し付けを行った場合は刑事罰の対象とされます。
まとめ
このように、2010年6月17日以前に契約した借入れの場合、過払金が発生している可能性が高いと言えます。過払金とは、グレーゾーン金利での貸付によって、払い過ぎてしまったお金のことをいいます。過払金が発生している場合であれば、払い過ぎてしまった金額を変換請求することができます。しかし、過払金変換請求権には消滅時効があり、最後に取引をした時から10年間が過ぎてしまうと請求できなくなってしまいます。したがって、2010年6月17日以前の契約によって、違法な金利で返済し、最後の取引が現在から遡って10年以内である場合であれば、過払金の変換請求ができる可能性があります。また、完済後に長い期間を開けずに同じ業者から再び借入れした場合においても、過払金請求が認められた事例もあります。消滅時効の起算点を判断するのは非常に難しいため、心当たりのある方は、直ちに専門家に相談することをお勧めします。